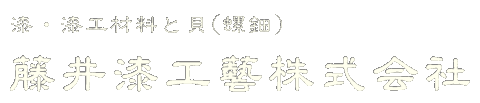広重製漆刷毛(ひろしげせいうるしばけ)
女性の髪の毛を藁灰汁で洗浄し、選り分けした後、良質の毛を漆にて固め乾燥し、ヒノキの薄板で包み込んで作ります。使用する髪の毛の中でも赤毛のものが良質です。
現在では漆刷毛を製作する職人の方も少なくなり、九世 泉 清吉 さんが製作した刷毛です。
本通し、半通し、改通し(あらためどおし)、立交(たてまぜ)、胴摺(どうずり)、刷毛目(はけめ)、泡消し、乾漆(かんしつ)など毛の長さや使用方法により様々な刷毛があります。
| 本通し(ほんとおし) | 毛先から最後まで毛が通してあります。 | ||
|---|---|---|---|
| 半通し(はんとおし) | 毛先から半分位まで毛が通してあります。 | ||
| 改通し(あらてめとおし) | 下塗り繊用の刷毛です。本通しになっています。 | ||
| 立交(たてまぜ) | 髪の毛の上下を馬毛ではさんだ、腰の強い、粘い漆用の刷毛。 | ||
| 胴摺(どうずり) | 木地に漆を摺り込む時に使用します。馬毛で作られています。 | ||
| 刷毛目(はけめ) | 刷毛目塗り用の馬毛の刷毛です。 | ||
| 泡消し(あわけし) | 漆の塗り面をそっとなでると塗面にできた泡をきれいに消すことができる刷毛です。 | ||
| 乾漆(かんしつ) | 乾漆を製作する際、麻布などの布を型に重ねて貼り付ける時に使用します。 |
その他、お客様のご要望にお応えして製作できますのでお気軽にご相談ください。
商品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
藤特選本通 (上塗り用)
| 3寸 | 55,000円 |
| 2寸5分 | 45,760円 | |
| 2寸 | 35,530円 | |
| 1寸8分 | 30,470円 | |
| 1寸5分 | 25,410円 | |
| 1寸2分 | 20,350円 | |
| 1寸 | 17,820円 | |
| 8分 | 15,290円 | |
| 6分 | 9,350円 | |
| 5分 | 9,350円 | |
| 3分 | 6,820円 | |
| 2分 | 6,820円 | |
| 1分 | 6,820円 |
商品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
藤特選半通 (上塗り用)
| 3寸 | 42,350円 |
| 2寸5分 | 33,880円 | |
| 2寸 | 25,410円 | |
| 1寸8分 | 22,880円 | |
| 1寸5分 | 18,700円 | |
| 1寸2分 | 15,290円 | |
| 1寸 | 12,760円 | |
| 8分 | 10,230円 | |
| 6分 | 7,700円 | |
| 5分 | 7,700円 | |
| 3分 | 5,170円 | |
| 2分 | 5,170円 | |
| 1分 | 5,170円 |
戻る『漆と漆工材料の販売』
商品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
藤特選1/3通 (上塗り用)
| 1寸 | 13,200円 |
| 8分 | 11,000円 | |
| 5分 | 8,800円 |
戻る『漆と漆工材料の販売』
商品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
乾漆刷毛半
| 1寸 | 14,300円 |
| 8分 | 11,000円 | |
| 5分 | 8,800円 |
戻る『漆と漆工材料の販売』
商品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
乾漆刷毛
| 8分 | 7,700円 |
| 5分 | 5,500円 |
戻る『漆と漆工材料の販売』
商品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
胴摺 半通し (馬毛硬め・馬毛軟目・髪毛の3種)
| 2寸 | 29,700円 |
| 1寸8分 | 27,500円 | |
| 1寸5分 | 24,200円 | |
| 1寸2分 | 19,800円 | |
| 1寸 | 18,700円 | |
| 8分 | 14,300円 | |
| 6分 | 11,000円 | |
| 5分 | 11,000円 | |
| 3分 | 9,900円 | |
| 2分 | 9,900円 | |
| 1分 | 9,900円 |
商品名 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
胴摺 1/3通し (馬毛硬め・馬毛軟目・髪毛の3種)
| 2寸 | 20,900円 |
| 1寸8分 | 18,700円 | |
| 1寸5分 | 16,500円 | |
| 1寸2分 | 14,300円 | |
| 1寸 | 12,100円 | |
| 8分 | 9,900円 | |
| 6分 | 6,600円 | |
| 5分 | 6,600円 | |
| 3分 | 5,500円 | |
| 2分 | 5,500円 | |
| 1分 | 5,500円 |
ご注文はこちら

クレジットカード・コンビニ・ キャリア決済も ご利用いただけます
------------------------------------
"クレジット決済"
(メールリンクサービス)
東京足立店頭で使えます!!